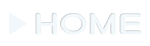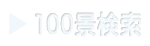西山寺とは?
静岡県牧之原市にある、かつて和歌にも詠まれ、堂塔12を抱え境内地3436坪を有した、825年に弘法大師 空海により開かれた高野山真言宗の古刹。山号を「医王山」と称し、御本尊として藤原時代の作である木造薬師瑠璃光如来像を安置する。戦国時代に、武田氏の遠江侵攻の兵火に遭い多くの堂宇を焼失。戦火を逃れた玉泉坊を本堂とする。江戸時代に入り、1636年に「薬師堂」を再建。徳川家庇護のもと、1712年に現在地に堂宇を移す。南北朝時代の1334年の鋳銅製の鳴り物仏具の「磬(けい)」や、左甚五郎の高弟 中山伊平次の作と伝えられる龍の彫刻がある「山門」、お騒がせ者の仁王の民話が残る「仁王門」などがある。
この時期がおすすめ!
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
名 称西山寺
ふりがなさいさんじ
ローマ字Saisan-ji Temple
地 区牧之原市(Makinohara City)
住 所牧之原市西山寺202
お問合せ0548-54-0111
するナビ牧之原市の観光スポット
西山寺のPR
西山寺の評価


1本堂まで必ず行こう!
本坊で落胆して帰らぬように!石段上に本堂が見える仁王門からが、この寺の魅力だよ!
2龍の彫刻を見逃すな!
すんなり山門をくぐってはいけない!必ず見上げて、左甚五郎の高弟の作品を見よう!
3ユニークな金剛力士像に注目!
サルスベリに登って難を逃れた仁王の民話や、口髭を生やしたその姿に注目!
西山寺 編
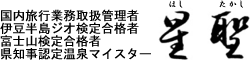

西山寺の地図
西山寺の見所

かつて堂塔12を抱えていたという古刹で、今川家・徳川家の庇護のもと繁栄。現在は衰退してしまったが、所々にその面影が垣間見れる。

遠目には影でわからなかったが、知らずに近づいて彫りの素晴らしさに驚いた。聞けば、江戸の名工 左甚五郎の高弟の中山伊平次の作とか・・・

山門をくぐり正面に本堂!?と思いきや、ここは生活空間である本坊。間違ってもここで落胆して引き返してはいけない!

全国に空海が開いたと伝わるお寺は、いったいどれだけあるのだろうか?といつも思う。ここも825年に、弘法大師により開かれた寺の一つだ。

和歌にも詠まれ、「蛭ヶ谷の田遊び」のルーツの寺であり、昭和の初め頃までは神楽舞も有名だったという。民俗芸能に深く結びついた寺だ。

ここにドウモコウモに追われ、観音様にすがり隣のサルスベリによじ登って命拾いをしたという民話が残る、傲慢だったお騒がせ者の仁王がいる。

力自慢で厄介者だった口髭をたくわえた金剛力士の吽形。改心してからは仏様の門番に!運慶作との伝承もあるが、さすがにそれは・・・

こちらも口髭が印象的な金剛力士の阿形。伽王(がおう)というのはよくわからないが、フレディー・マーキューリーに似ているとして密かに人気に!

国の重要無形文化財である蛭子神社の「蛭ヶ谷の田遊び」は、かつて西山寺に伝わっていたもので、この石段をもらい受けるために譲渡されたとか…

江戸時代の1636年に建てられ移築された、間口5.4m 奥行6.4mの木造茅葺方形造の本堂。1967年10月11日に、静岡県指定文化財となっている。