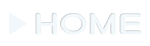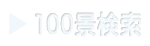間眠神社とは?
静岡県三島市東本町の下田街道沿いにある、食物を司る女神である豊受姫命(とようけひめのみこと)を祀る神社。1180年に「蛭ヶ小島」に流されていた源頼朝が、「三嶋大社」に源氏再興の願を立て百日参籠をする中、狩野川の大氾濫により、旧韮山町長崎の稲荷社よりこの地に流れ着いていた路傍の祠の松の根本でまどろんだという伝承地で、後に社が造営され「間眠稲荷」「間眠宮」と呼ばれるようになった。毎年8月1日の例大祭になると、約6km離れた伊豆の国市長崎の人々が、800年以上も続くとされる行事である、恵みをもたらした稲わらを編み込んだ長さ約3m 胴周約1.8m 重さ約80kgにも及ぶ大注連縄を奉納する。
この時期がおすすめ!
| 1月元旦祭 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月祭典 | 8月例大祭 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
名 称間眠神社
ふりがなまどろみじんじゃ
ローマ字Madoromi Jinja Shrine
地 区三島市(Mishima City)
住 所三島市東本町2-11-35
お問合せ055-971-5000(三島市観光協会)
するナビ三島市の観光スポット
間眠神社のPR
間眠神社の評価


1大注連縄を見逃すな!
長さ約3m 胴周約1.8m 重さ約80kgにも及ぶ大注連縄だよ!
2源頼朝ゆかりの神社だよ!
三嶋大社に百日参籠の中、頼朝が微睡んだという路傍の祠の松の地に建つ神社だよ!
3毎年8月1日の例大祭へ行ってみよう!
毎年、約6km離れた韮山より大注連縄が奉納される。800年以上も続くから驚く!
間眠神社 編
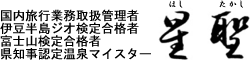

間眠神社の地図
間眠神社の見所

「三嶋大社」から約700mの下田街道沿いに、白っぽい台輪鳥居が目印の、食物・穀物を司る女神を祀る間眠神社がある。

毎年8月1日の例大祭になると、かつて祠があった約6km離れた韮山より、長さ約3m 胴周約1.8m 重さ約80kgに及ぶ大注連縄が奉納される。

元々流されて来た祠があった伊豆の国市長崎は、平安時代末に源頼朝が「三嶋大社」に寄進した地だ。これも何かの縁なのだろう。

台輪鳥居をくぐると、いかにも古そうないくつかの常夜燈や祠・石碑などが建っている。刻まれた三嶋大明神や常夜燈の文字が、歴史を感じさせる。

春になると、子供たちの遊ぶ声が響く間眠神社に隣接した間眠公園に桜が咲く。祭りの時には、ここが大賑わいとなる。

現在は住宅密集地だが、境内からはかろうじて富士山が見える。頼朝もここから、こうして富士山を望みながら眠りに入ったのだろう。