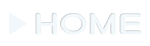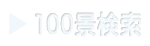頼朝の井戸の森とは?
静岡県裾野市を走る国道469号線沿いにある、ブナやケヤキ・カエデなどの落葉樹が生い茂げ野鳥がさえずる、裾野市の天然記念物に指定されている原生林の森。鎌倉幕府の初代征夷大将軍である源頼朝が、1193年5月に富士山麓において1ヶ月にも及び催した「富士の巻狩り」の際に、本陣近くのこの森にあった小湖となした湧水のその味にいたく感銘し、手にした朱のお椀を水神に献じるため、その水面より沈めたと伝わる森。かつては一面が湿地帯で、森のあちこちの窪地には泉が湧出していて一年中涸れることがなかったとされる。
この時期がおすすめ!
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月紅葉 | 12月 |
名 称頼朝の井戸の森
ふりがなよりとものいどのもり
ローマ字Forest of the Yoritomo's well
地 区裾野市(Susono City)
住 所裾野市須山2255-1000
お問合せ055-992-5005(裾野市観光協会)
するナビ裾野市の観光スポット
頼朝の井戸の森のPR
頼朝の井戸の森の評価


1紅葉シーズンがおすすめ!
ケヤキやカエデなどの落葉樹が紅葉する11月に訪れよう!
2富士の巻狩りについて学ぼう!
井戸を見てどうよというより、頼朝公の巻狩りについての歴史や伝説に耳を傾けよう!
3水原秋桜子の句碑にも注目!
頼朝公の巻狩りとは直接関係ないが、水原秋桜子の句碑もあるので見逃さずに!
頼朝の井戸の森 編
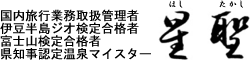

頼朝の井戸の森の地図
頼朝の井戸の森の見所

現在ではナビやスマホのお陰で迷わずたどり着けるが、昔はこんな案内板の存在が貴重だった。倒れているだけで迷ったものだ・・・

奥へと進んでいくと、東屋が見え、その一体が開けており、森という感じはしない。ここでいいのか?と一瞬思ったり・・・

頼朝の井戸の森の樹木たち
森らしくない?頼朝の井戸の森を構成している樹木は、実に多種多様だ。ブナやケヤキ・カエデの他、ミズナラやコナラ、ミズキやヤマボウシなどの高木と、リョウブやエゴノキ、富士桜にミツバツツジ、そしてこのエリア特有のアシタカツツジなどの中低木も混在している。

頼朝の井戸
今ではこうして井戸の形をしているが、当初は湧水が溜まり泉を超え、小さな湖のような池を形成していたとされる。その池で、巻狩の際に頼朝公が沈めたとされる朱のお椀が地上より見える時は、天変地異の前兆だとして恐れられたという伝説が残されている。

もちろん頼朝の時代のモノでは無いが、井戸の横にはゆかりの水神社らしきものが建てられている。

石で組まれた井戸の口には蓋は無く、落下防止の鉄格子と周囲に柵が設けられている。井戸の中がどうなっているのかは?だ。

頼朝の井戸と刻まれた、1973年11月25日に、裾野市の観光協会により建立された石碑。結構大きい。

1959年に開かれた探鳥句会において、水原秋桜子が草を背負い行く童女を詠んだ「ほととぎす 朝は童女も 草を負う」の句碑が建てられている。