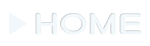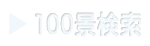長源寺とは?
静岡県伊豆の国市韮山にある「修禅寺」の末寺で、山号を「天與山(てんよざん)」と称する、伊豆八十八ヵ所霊場の第11番札所となっている曹洞宗寺院。創建年代は不詳だが、北條早雲が「石雲院」より虚庵玄充を招き入れたとの記述が残ることから、室町時代の開創と考えられている。御本尊として釈迦如来像を安置する他、境内には「水かけ観音」やトイレの神様である「烏枢沙摩明王」を祀るお堂もあり、毎年8月25日には、例祭も執り行われる。
この時期がおすすめ!
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月例祭 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
名 称長源寺
ふりがなちょうげんじ
ローマ字Chogen-ji Temple
地 区韮山/伊豆の国市(Nirayama/Izunokuni City)
住 所伊豆の国市中492-2
お問合せ055-949-5420
するナビ伊豆の国市の観光スポット
長源寺のPR
長源寺の評価


1伊豆八十八ヶ所の札所だよ!
伊豆八十八ヶ所の第11番札所で、札所では数少ない富士山の眺望が楽しめるお寺だよ!
2トイレの神様は"おまたぎ"で!
トイレの神様である烏枢沙摩明王のお参り時は、例に従い"おまたぎ"しよう!
3水かけ観音も忘れずにお参りしよう!
水かけコロリ観音とも呼ばれており、延命や無病息災のご利益があるとされているよ!
長源寺 編
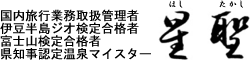

長源寺の地図
長源寺の見所

比較的新しい構えを見せる長源寺。この山門を背にして望む富士山が美しい。実は伊豆八十八ヶ所の札所で、富士山が望める寺は限られている。

お寺の門を潜るとき、あちこちのお寺で出迎えてくれるのが六地蔵だ。何気に並んでいるようで、お寺ごとの個性が光るお地蔵様でもある。

禅寺らしくお掃除や草木の剪定など、隅々まで手入れの行き届いた境内で、一歩足を踏み入れただけで、気持ちが晴れ晴れする。

1965年に移築された後、平成の改修工事を経て趣を増したコンクリート造の本堂は、現在の様な堂々とした姿となっている。

本堂の格天井には、菊や水仙などの花の天井画が描かれており、正面に御本尊であり札所本尊ともなっている釈迦如来像が安置されている。

伊豆でトイレの神様と言えば「明徳寺」が有名だが、ここにも烏枢沙摩明王を祀るお堂がある。お参り方法も、例の"おまたぎ"だ・・・。

釈迦如来像が札所本尊となっている伊豆八十八ヶ所の第11番札所で、御詠歌は『尊きや 天の与えし 法の山 めぐみたえすぬ 長きみなもと』だ。

「水かけコロリ観音」とも呼ばれている、延命や無病息災のご利益があるとされる観音様だ。例に従い、きちんとお参りしておこう!

純白や桃色・赤紫など、実に様々な色の花を咲かせるサルスベリ。長源寺でも、毎年8月~9月にかけて、美しい花が楽しめる。

サルスベリは、彩りの少ない夏~秋にかけて、百日紅の名の通りに比較的長い間美しい花を咲かせており、個人的にも大好きな花の1つだ。

サルスベリと時を同じくして咲くのが、ニワトリのトサカに似ていることからその名がついたケイトウ(鶏頭)だ。マジマジ見るとオモシロい。

境内を奥に進んでいくと、一気に開け、一段低くなった広大な敷地が広がっている。その奥に墓地があるが、ここがかつての本堂跡だ。

立派な石垣が築かれている、かつて伽藍があった広大な敷地の一角に、樹木で象られ浮き彫りとなった長・源・寺の文字が見て取れる。

境内にはたくさんの大きな天然石があるが、これらは世界遺産の「韮山反射炉」前に店を構える蔵屋鳴沢の稲村宣氏の寄贈で、この彫刻もその1つだ。