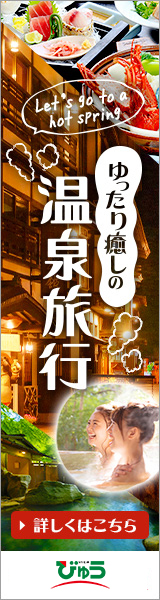♨ 温泉とは?

火山列島である日本には2021年3月末現在、2,934ヵ所の温泉地があり、27,969ヵ所の源泉が確認されている。このサイトを立ち上げた当初の2006年3月末には、3,162ヵ所の温泉地があり、27,866ヵ所の源泉が確認されていたので、環境省の集計方法が変わっていなければ、温泉地は▲228減り、源泉数は103増えた計算になる。
♨ 実はゆる~い温泉基準!
そんな温泉だが、地上に湧き出ている温泉もあれば、地下何千メートルというボーリングによりやっと噴出した温泉もあり、ひとえに「温泉」と言ってもその種類はいろいろであり、中には首を傾げたくなるものもある。
そもそも温泉とは、1948年7月10日に制定、2011年8月30日に最終改正されている 温泉法 で「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表①に掲げる温度又は物質を有するもの」と定義されている。つまり地中から湧き出る
① 温水
② 鉱水
③ 水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)
のいずれかであり、別表①に掲げる
条件①:泉源から採取されるときの温度が 摂氏25度以上のもの
条件②:温度に関係なく、下記物質をいずれか1つ限界値以上含むもの
| 19種の物質一覧 | ||
| No | 物質名 | 含有量(1kg中) |
|---|---|---|
| 1 | 溶存物質(ガス性のものを除く) | 総量1000mg以上 |
| 2 | 遊離炭酸(CO2)(遊離二酸化炭素) | 250mg以上 |
| 3 | リチウムイオン(Li+) | 1mg以上 |
| 4 | ストロンチウムイオン(Sr2+) | 10mg以上 |
| 5 | バリウムイオン(Ba2+) | 5mg以上 |
| 6 | フェロ 又は フェリイオン(Fe2+ , Fe3+) (総鉄イオン) |
10mg以上 |
| 7 | 第一マンガンイオン(Mn2+) (マンガン(Ⅱ)イオン) |
10mg以上 |
| 8 | 水素イオン(H+) | 1mg以上 |
| 9 | 臭素イオン(Br-)(臭化物イオン) | 5mg以上 |
| 10 | 沃素イオン(I-)(ヨウ化物イオン) | 1mg以上 |
| 11 | ふっ素イオン(F-)(フッ化物イオン) | 2mg以上 |
| 12 | ヒドロひ酸イオン(HASO42-) (ヒ酸水素イオン) |
1.3mg以上 |
| 13 | メタ亜ひ酸(HASO2) | 1mg以上 |
| 14 | 総硫黄(S) [HS-+S2O32-+H2Sに対応するもの] |
1mg以上 |
| 15 | メタほう酸(HBO2) | 5mg以上 |
| 16 | メタけい酸(H2SiO3) | 50mg以上 |
| 17 | 重炭酸そうだ(NaHCO3) (炭酸水素ナトリウム) |
340mg以上 |
| 18 | ラドン(Rn) | 20(100億分の1キュリー単位)以上 |
| 19 | ラジウム塩(Raとして) | 1億分の1mg以上 |
となり、条件①②のどちらかを満たしていればよいとされている。
逆に言えば、この条件さえクリアしていればすべて「温泉」と成りえるわけで、成分的にはただの水と思われるものでも、25℃以上あればそれはれっきとした「温泉」であり、また逆に冷たくても、指定物質を1つでも限界値以上含んでいれば、それもまた「温泉」なのである。
まずはこのことを正確に理解していただきたい。
♨ 掘るだけで温泉に!?
その上でもう一つ大事なポイントとなっているのが、ボーリングによりどんどん深く掘っていけば、地熱により水温は上昇するという事実である。
一概には言えないが、掘削深度による水温の上昇は、100mで2~3℃とされている。つまり1000mボーリングすれば、地表水温に20~30℃プラスした温水が得られるわけで、地表で15℃なら35℃~45℃となり、それだけで「温泉」と成りえるのである。
もちろんそこに水脈があることが前提だが、掘削技術の進化と共に事実こうして掘られた温泉は数多く存在しており、近年の温泉ブームによりこの手の温泉が急増しているのも事実である。
例えば近年温泉が急増した大阪市では、100mで3.5℃以上水温の上昇が見られることから、掘削費用も安上がりで700mも掘れば温泉になり、おまけに人口も多いので、開業後の収益面でも有利と言われている。
これらすべてに?マークを付けるわけではないが、数千万をかけ地底奥深くから無理やり組み上げているような温泉がどのようなものなのか、入る側もただ「温泉」と言う言葉だけを鵜呑みにするのではなく、どんな「温泉」なのかを正しく学び理解する必要がある。
“地球の奥深く、地下1000mよりこんこんと湧く大地の恵み!”なんてキャッチに、簡単に踊らされてはいけないのである。
♨ 療養泉とは?
温泉法による「温泉」の定義とは別に、温泉の中で特に治療の目的に供しうるものを「療養泉」として区別している。その基準は、環境省の『鉱泉分析法指針』により定められており、
条件①:泉源から採取されるときの温度が 摂氏25度以上のもの
条件②:温度に関係なく、下記物質をいずれか1つ限界値以上含むもの
| 療養泉の物質一覧 | ||
| No. | 物質名 | 含有量(1kg中) |
|---|---|---|
| 1 | 溶存物質(ガス性のものを除く) | 総量1000mg以上 |
| 2 | 遊離炭酸(CO2)(遊離二酸化炭素) | 1000mg以上 |
| 6 | フェロ + フェリイオン(Fe2+ + Fe3+) (総鉄イオン) |
20mg以上 |
| 8 | 水素イオン(H+) | 1mg以上 |
| 10 | 沃素イオン(I-)(ヨウ化物イオン) | 10mg以上 |
| 14 | 総硫黄(S) [HS-+S2O32-+H2Sに対応するもの] |
2mg以上 |
| 18 | ラドン(Rn) | 30(100億分の1キュリー単位)以上 111Bq以上(8.25マッヘ単位以上) |
と、条項は温泉と同じだが、No.を基に上の温泉の表と比較していただければわかるように、1.溶存物質 と 8.水素イオン 以外は、赤字で示したように特定物質の限界値がより厳しいものとなっている。見落としがちだが、6.総鉄イオン の所が、「又は」から「+」に変わっている所も異なる。
そして一般的に知られている泉質名表記は、実はこの「療養泉」に与えられているものであり、療養泉の規定に達していないものは、泉質表記が無かったり、単に温泉法上の温泉と記載されているケースが多いようだ。
以上、ここでは温泉と療養泉について説明してきたが、日本人なら誰もが知っている「温泉」と言う言葉の裏に、実は難しい定義があることをご理解いただけたかと思う。
ただ、よく街角インタビューで「温泉って何?」の質問に、「えぇ~何だろう、あったかいお湯‼(笑)」なんて冗談めいた回答が聞かれるが、定義は難しいが巡り巡って当たらずといえども遠からず…という感じになってしまうのが「温泉」だ。
これがまた笑えることなのだが、その実態は笑えない。
♨ タオル のことまで 環境省が…!?
ちなみに、温泉入浴時の注意事項が 環境省 により定められているので、紹介しておこう。ほぼ原文通りなので読みづらいですが、
①浴用の方法及び注意
温泉の浴用は、以下の事項を守って行う必要がある。
ア.入浴前の注意
(ア) 食事の直前、直後及び飲酒後の入浴は避けること。酩酊状態での入浴は特に避けること。
(イ) 過度の疲労時には身体を休めること。
(ウ) 運動後30分程度の間は身体を休めること。
(エ) 高齢者、子供及び身体の不自由な人は、1人での入浴は避けることが望ましいこと。
(オ) 浴槽に入る前に、手足から掛け湯をして温度に慣らすとともに、身体を洗い流すこと。
(カ) 入浴時、特に起床直後の入浴時などは脱水症状等にならないよう、あらかじめコップ一杯程度の水分を補給しておくこと。
イ.入浴方法
(ア) 入浴温度
高齢者、高血圧症若しくは心臓病の人又は脳卒中を経験した人は、42℃以上の高温浴は避けること。
(イ) 入浴形態
心肺機能の低下している人は、全身浴よりも半身浴又は部分浴が望ましいこと。
(ウ) 入浴回数
入浴開始後数日間は、1日当たり1~2回とし、慣れてきたら2~3回まで増やしてもよいこと。
(エ) 入浴時間
入浴温度により異なるが、1回当たり、初めは3~10分程度とし、慣れてきたら15~20分程度まで延長してもよいこと。
ウ.入浴中の注意
(ア) 運動浴を除き、一般に手足を軽く動かす程度にして静かに入浴すること。
(イ) 浴槽から出る時は、立ちくらみを起こさないようにゆっくり出ること。
(ウ) めまいが生じ、又は気分が不良となった時は、近くの人に助けを求めつつ、浴槽から頭を低い位置に保ってゆっくり出て、横になって回復を待つこと。
エ.入浴後の注意
(ア) 身体に付着した温泉成分を温水で洗い流さず、タオルで水分を拭き取り、着衣の上、保温及び30分程度の安静を心がけること(ただし、肌の弱い人は、刺激の強い泉質(例えば酸性泉や硫黄泉等)や必要に応じて塩素消毒等が行われている場合には、温泉成分等を温水で洗い流した方がよいこと。)。
(イ) 脱水症状等を避けるため、コップ一杯程度の水分を補給すること。
オ.湯あたり
温泉療養開始後おおむね3日~1週間前後に、気分不快、不眠若しくは消化器症状等の湯あたり症状又は皮膚炎などが現れることがある。このような状態が現れている間は、入浴を中止するか、又は回数を減らし、このような状態からの回復を待つこと。
カ.その他
浴槽水の清潔を保つため、浴槽にタオルは入れないこと。
…とまぁ、アイウエオというのがお役所らしいですが、ビックリしたのがタオルは入れないこと!…、ここまで細かく決められているんですね。
常識だろ!と思われることでも、もはや掲示しないと通用しない時代なんですね。
♨ 温泉入門 目次